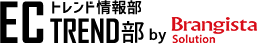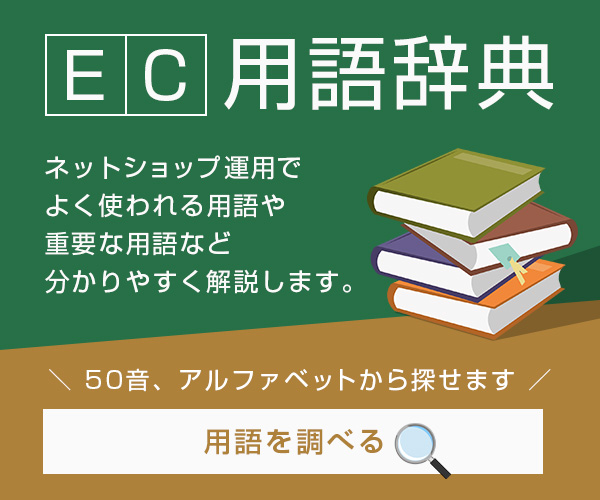JANコードの基礎知識:意味と内容の解説
公開日:
更新日:

この記事では、JANコードの基礎知識からその読み方、活用方法に至るまでを詳細に解説します。
JANコードは単なる数字の羅列ではなく、商品管理や在庫管理、データ分析など、ビジネスの効率化に不可欠な役割を果たしています。
また、この記事ではJANコードの生成と登録のプロセス、さらには他のバーコードシステムとの違いにも触れ、
JANコードの理解を深めることで、その知識を日常生活やビジネスシーンで如何に活用できるかを探ります。
テクノロジーの進化と共に変わりゆくJANコードの未来にも焦点を当て、読者の皆様にとって有益な情報を提供いたします。
1. JANコードとは?

皆さんが日々のお買い物でよく目にするバーコード、その中でも特に「JANコード」と呼ばれるものがあります。
これは、商品を一意に識別するための国際標準のコードで、日本国内ではほぼ全ての商品に印刷されています。
JANコードは、商品の管理や販売、在庫の確認など、ビジネスの現場で欠かせない役割を担っているのです。
このセクションでは、そんなJANコードの基本的な定義から、その構造に至るまでをわかりやすく解説していきます。
1-1. JANコードの歴史
皆さんがレジで商品を購入する際にピッと読み取られるJANコード。この便利なコードがいつから私たちの生活に溶け込んでいるのか、ご存知ですか?
実は、JANコードは1978年に日本で初めて導入されました。これは、商品の効率的な管理と流通を目的として開発されたものです。
当時、商品の管理は手作業によるものが主流でしたが、JANコードの登場により、商品情報の正確な読み取りと迅速な処理が可能になりました。
このコードは、日本国内で統一された商品識別コードとして、小売業界を中心に急速に普及。
やがて、国際標準化機構(ISO)によって国際標準として認められ、現在では世界中で広く使用されているのです。
JANコードの導入は、商品管理のみならず、消費者のショッピング体験をも大きく変えたと言えるでしょう。
1-2. JANコードの構造
JANコードは、商品を一意に識別するためのバーコードシステムですが、その構造にはどのような意味が込められているのでしょうか。
JANコードは通常、13桁の数字で構成されています。最初の2桁は国コードで、日本の場合は「49」が割り当てられています。
次の5桁はメーカーコード、これはメーカーごとに異なり、商品を製造する企業を示します。
続く5桁は商品コードで、メーカー内でその商品を特定するための番号です。
最後の1桁はチェックディジットと呼ばれ、これまでの12桁の数字をもとに計算されることで、読み取りエラーを防ぐ役割を果たしています。
このように、JANコード一つ一つには、商品の出所から品質管理まで、多くの情報が詰め込まれているのです。
これらの数字を正確に読み取ることで、私たちは迅速かつ正確な商品管理を行うことができるのです。
2. JANコードの読み方
日々の買い物でよく目にするJANコード。しかし、その黒い線と数字の羅列が何を意味しているのか、詳しく知っている人は少ないかもしれません。
JANコードは、商品を一意に識別するための国際的なコードシステムです。
このコードを読み解くことで、商品の原産国やメーカー、商品自体の情報が分かります。
読み方の基本は、左側の数字が国や地域を、中央の数字がメーカーやブランドを、右側の数字が商品を指しています。
解読のコツは、まずはこの基本構造を覚えることから始めましょう。
2-1. 数字の意味
JANコードは、商品を一意に識別するための数字の羅列ですが、一体どんな情報が込められているのでしょうか。
このコードは、通常13桁から構成され、それぞれの数字には特定の意味があります。最初の2桁は国コードで、日本の場合は「45」または「49」が割り当てられています。
次の5桁はメーカーコードで、商品を製造・販売する企業を示します。続く5桁は商品コードとなり、それぞれの商品やバリエーションを区別します。
最後の1桁はチェックディジットと呼ばれ、これまでの数字が正しいかどうかを確認するためのものです。
このように、JANコード一つ一つには、商品の出所から種類まで、豊富な情報が詰まっているのです。
これらの情報を理解することで、消費者はもちろん、ビジネスにおいても商品管理や流通の効率化に役立てることができます。
2-2. チェックディジット
JANコードの最後に位置するチェックディジットは、コードの正確性を保証する重要な役割を果たします。
この数字は、コードが正しく読み取られたかどうかを確認するためのもので、誤りを防ぐためのセーフティネットのような存在です。
具体的には、先行する12桁の数字を特定の計算式に従って計算し、その結果から導き出される1桁の数字がチェックディジットとなります。
この計算により、たとえばバーコードリーダーが誤って数字を読み取った場合でも、そのエラーを検出し、誤ったデータの入力を防ぐことができるのです。
つまり、チェックディジットはJANコードの信頼性を高め、消費者に正確な商品情報を提供するために不可欠な要素と言えるでしょう。
また、ビジネスの現場では、このチェックディジットを利用して、在庫管理や販売データの精度を向上させることが可能です。
JANコードのこの部分に注目することで、より確実な商品管理が実現し、効率的なビジネス運営に貢献するのです。
3. JANコードの活用方法

JANコードは、商品の識別だけでなく、ビジネスの効率化にも大きく貢献しています。
例えば、小売業界では、商品の入荷から販売、在庫管理に至るまで、JANコードを活用することで、作業の自動化とスピードアップが実現されています。
また、販売データの収集にも役立ち、消費者の購買傾向の分析やマーケティング戦略の策定に不可欠な情報を提供してくれます。
このように、JANコードは単なる番号ではなく、ビジネスの成長を支える重要なツールなのです。
3-1. 在庫管理
商品の流通や販売において、在庫管理は極めて重要なプロセスです。
JANコードは、この在庫管理を効率化し、正確性を高めるために不可欠なツールとなっています。
具体的には、JANコードをスキャンすることで、商品の入出庫の記録が瞬時に行え、在庫の正確な数をリアルタイムで把握することが可能です。
また、JANコードを活用することで、商品の過剰在庫や品切れを防ぐことができ、需要予測に基づいた在庫の最適化にも寄与します。
さらに、JANコードを組み込んだ在庫管理システムを導入することで、商品のピッキングや棚卸作業の時間短縮にも繋がります。
これにより、作業効率の向上だけでなく、人的ミスの削減にも効果を発揮し、結果としてコスト削減にも貢献するのです。
JANコードを駆使した在庫管理は、ビジネスの競争力を高めるためにも、今や不可欠な存在と言えるでしょう。
3-2. 販売データの分析
販売データの分析は、商品の市場動向を理解し、ビジネス戦略を練る上で欠かせない要素です。
JANコードを活用することで、販売された商品の情報が瞬時にデータベースに蓄積され、これらのデータを基に詳細な分析が可能になります。
例えば、どの商品がどの地域でよく売れているのか、季節やイベントによって売上が変動する商品は何か、といった消費者の購買パターンを把握することができます。
また、JANコードによるデータ収集は、時間帯や曜日別の売上分析にも役立ち、効果的なプロモーションや在庫補充のタイミングを見極めるのにも有効です。
さらに、販売データの長期的なトレンド分析を行うことで、将来の市場の需要を予測し、新商品開発や販売戦略の策定にも活かすことができるのです。
JANコードを用いた販売データの分析は、顧客満足度の向上や売上アップに直結するため、ビジネスの成長を加速させる強力なツールとなります。
4. JANコードの生成と登録
自社商品に固有の識別子を与えるJANコード。その生成から登録までのプロセスは、商品の流通や管理において欠かせない要素です。
JANコードを自分で生成するには、まず商品情報を整理し、正しいフォーマットでコードを作成する必要があります。
そして、生成したコードを日本流通自主管理協会(JAN協会)に登録し、公式な商品コードとして認定を受けることが重要です。
この手続きを通じて、商品は市場で正しく識別され、効率的な流通が可能になります。
4-1. JANコードの生成
商品を市場に出す際、JANコードの生成は必須のステップです。では、どのようにしてJANコードを生成するのでしょうか。
まず、JANコードは日本で使用されるバーコードの一種で、商品の識別に役立ちます。生成には、商品のカテゴリーやメーカー情報が必要となります。
具体的には、JANコードの最初の7桁はメーカーコードとして、日本記事番号協会に登録し取得します。
次の5桁は商品固有の番号で、メーカーが自由に割り当てることができます。最後の1桁はチェックディジットと呼ばれ、誤りを防ぐための数字です。
このチェックディジットは、他の数字を特定の計算式に当てはめることで導き出されます。
JANコードの生成には専用のソフトウェアが便利で、正確なコードを簡単に作成することが可能です。
自社商品に適したJANコードを生成し、流通の効率化と管理の正確性を高めましょう。
4-2. JANコードの登録
生成したJANコードを市場で使用するためには、正式な登録が必要です。
この登録プロセスは、商品の流通をスムーズにし、消費者に安心を提供するためにも重要な手続きとなります。
まず、日本記事番号協会の公式ウェブサイトにアクセスし、必要な情報を入力して申請を行います。申請には、企業情報や商品情報、生成したJANコードが必要です。
申請が承認されると、そのJANコードは正式に登録され、全国の小売店やオンラインショップでの販売が可能になります。
また、登録後はJANコードのデータベースに情報が記録され、消費者が商品をスキャンすることで、その商品に関する詳細情報を得ることができるようになります。
正確な登録を行うことで、商品のトレーサビリティが向上し、万が一のリコール時にも迅速な対応が可能となります。
JANコードの登録は、商品の信頼性を高めるだけでなく、効率的な商品管理にも寄与するため、ビジネスにおいて非常に重要なプロセスです。
5. JANコードと他のバーコード
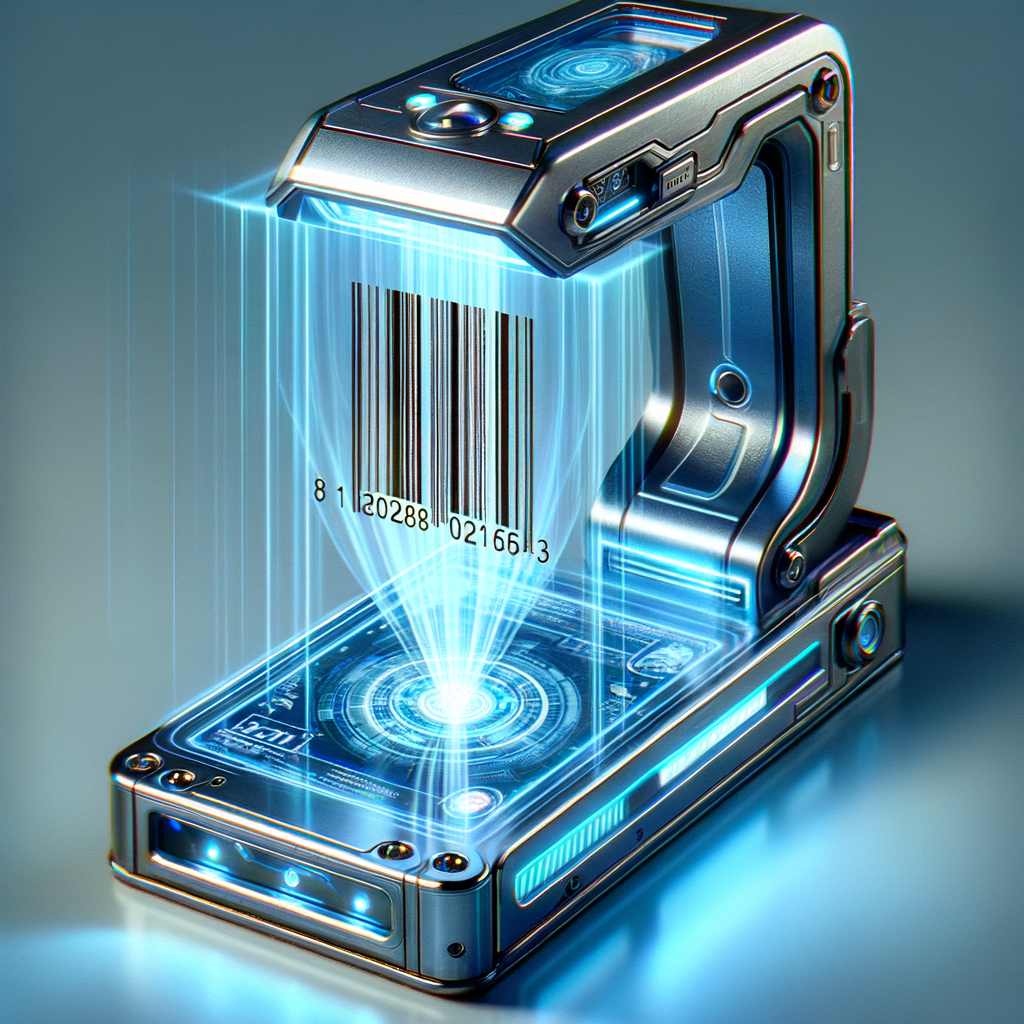
日本で広く利用されているJANコードですが、世界には様々なバーコードシステムが存在します。
例えば、北米で主流のUPCコードは、JANコードと似ていますが、国コードが異なる点が特徴です。
また、QRコードは情報量が多く、二次元コードとしての利点を持っています。これらのバーコードはそれぞれに独自の特性を持ち、用途に応じて使い分けられています。
JANコードの独自性と他のバーコードとの違いを理解することで、より効果的な商品管理や情報伝達が可能になります。
5-1. UPCコードとの違い
日本で広く利用されているJANコードと、北米で主流のUPCコード。これらはどちらも商品の識別に不可欠なバーコードシステムですが、いくつかの違いがあります。
まず、JANコードは「日本記事番号」とも呼ばれ、13桁の数字で構成されています。
一方、UPCコードは「ユニバーサル・プロダクト・コード」と称され、12桁の数字から成り立っています。
JANコードは国際的な規格であるEAN(EuropeanArticleNumber)に準拠しており、世界中で通用する設計になっています。
それに対し、UPCコードは主に北米で使用され、国際的な取引の場ではJANコードに変換する必要がある場合があります。
また、JANコードの最初の2桁は国コードであり、日本の場合は「49」が割り当てられています。
UPCコードには国コードが含まれていません。これらの違いを理解することで、国際的な商品流通においてスムーズな取引が可能となります。
5-2. QRコードとの比較
JANコードとQRコードは、どちらも情報をデジタル形式で表現するバーコード技術ですが、その用途と特徴には大きな違いがあります。
JANコードは主に商品の識別と追跡を目的としており、商品のパッケージに印刷された13桁の数字で構成されています。
これにより、販売時のレジでのスキャンや在庫管理が効率的に行えるようになっています。
一方、QRコードは「QuickResponseCode」の略で、情報量が多く、URLや名刺情報、決済情報などを含むことができます。
二次元コードとも呼ばれ、その格子状のパターンは、JANコードよりも複雑なデータを格納する能力を持っています。
スマートフォンなどのカメラで簡単に読み取ることができ、広告やチケット、電子決済など幅広い分野で活用されています。
JANコードが商品管理に特化しているのに対し、QRコードは多様な情報を伝達するための手段として利用される点が大きな違いです。
これらの特性を理解することで、ビジネスや日常生活において、それぞれのコードを適切に活用することができます。
6. JANコードの未来
テクノロジーが日々進化する中で、JANコードもまた新たな変革期を迎えています。
将来的には、さらに高速で正確な読み取りが可能になるスキャナーの開発、AIによる自動認識システムの導入、
あるいはバーチャルリアリティ(VR)や拡張現実(AR)を活用した新しいショッピング体験の提供など、JANコードの活用方法は多岐にわたる可能性を秘めています。
これらの技術革新は、商品管理や在庫管理をはじめとするビジネスプロセスを大きく変え、消費者にとってもより便利でスムーズな買い物が実現することでしょう。
6-1. テクノロジーの進化
JANコードは、商品の識別や在庫管理に不可欠なバーコードシステムですが、テクノロジーの進化により、その読み取り技術も日々進化しています。
従来のレーザースキャナーから、より高速で正確なイメージスキャナーへと変わりつつあり、これにより、商品の読み取りエラーが大幅に減少しました。
また、スマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイスを使用した読み取りアプリケーションも普及し、
小売業界だけでなく、個人の消費者にとってもJANコードの利便性が向上しています。
さらに、クラウドベースの在庫管理システムと連携することで、リアルタイムでのデータ分析や在庫の最適化が可能になり、ビジネスの効率化が進んでいます。
これらの技術革新は、JANコードの読み取り精度を高めるだけでなく、新たなビジネスモデルの創出にも寄与しており、今後もその進化に注目が集まっています。
6-2. 新しい活用シーン
テクノロジーの進化は、JANコードの活用シーンを拡大させています。
例えば、オンラインショッピングの増加に伴い、消費者が自宅で商品をスキャンし、瞬時に情報を取得し購入できるシステムが考えられます。
また、IoT技術の組み合わせにより、冷蔵庫が中の食品のJANコードを読み取り、消費期限の管理や買い物リストの自動生成を行う未来も近いかもしれません。
さらに、ブロックチェーンと連携して、商品の生産から消費者の手元に届くまでの流通履歴を透明にすることで、食品の安全性や偽造防止に貢献する可能性もあります。
これらの新しい活用シーンは、私たちの生活をより便利で安心なものに変えるだけでなく、ビジネスの新たな価値を生み出す原動力となるでしょう。
JANコードの未来は、ただ商品を識別するだけでなく、私たちの生活を豊かにする多様な可能性を秘めています。
まとめ
JANコードは、商品の識別と管理を効率化するために不可欠なツールです。
この記事では、JANコードの基本からその読み方、活用方法、さらには生成と登録のプロセスに至るまで、その全貌を明らかにしました。
また、UPCコードやQRコードとの違いを比較し、JANコードの独自性とその利点を掘り下げました。
テクノロジーの進化と共に、JANコードの未来についても考察し、新しい活用シーンの可能性を探りました。
読者の皆様がこの情報を活用し、日々の生活やビジネスシーンでの商品管理、在庫管理、データ分析に役立てることを願っています。
JANコードの理解を深め、その潜在能力を最大限に引き出すことで、よりスマートな消費者、またはビジネスパーソンになるための一歩を踏み出しましょう。

ブランジスタソリューションのマーケティングチームです。
ECやWEBの最新情報が大好きなメンバーが、Amazonや
楽天などのモールから自社EC、プロモーション等、販促情
報に関してあらゆることを発信していきます!